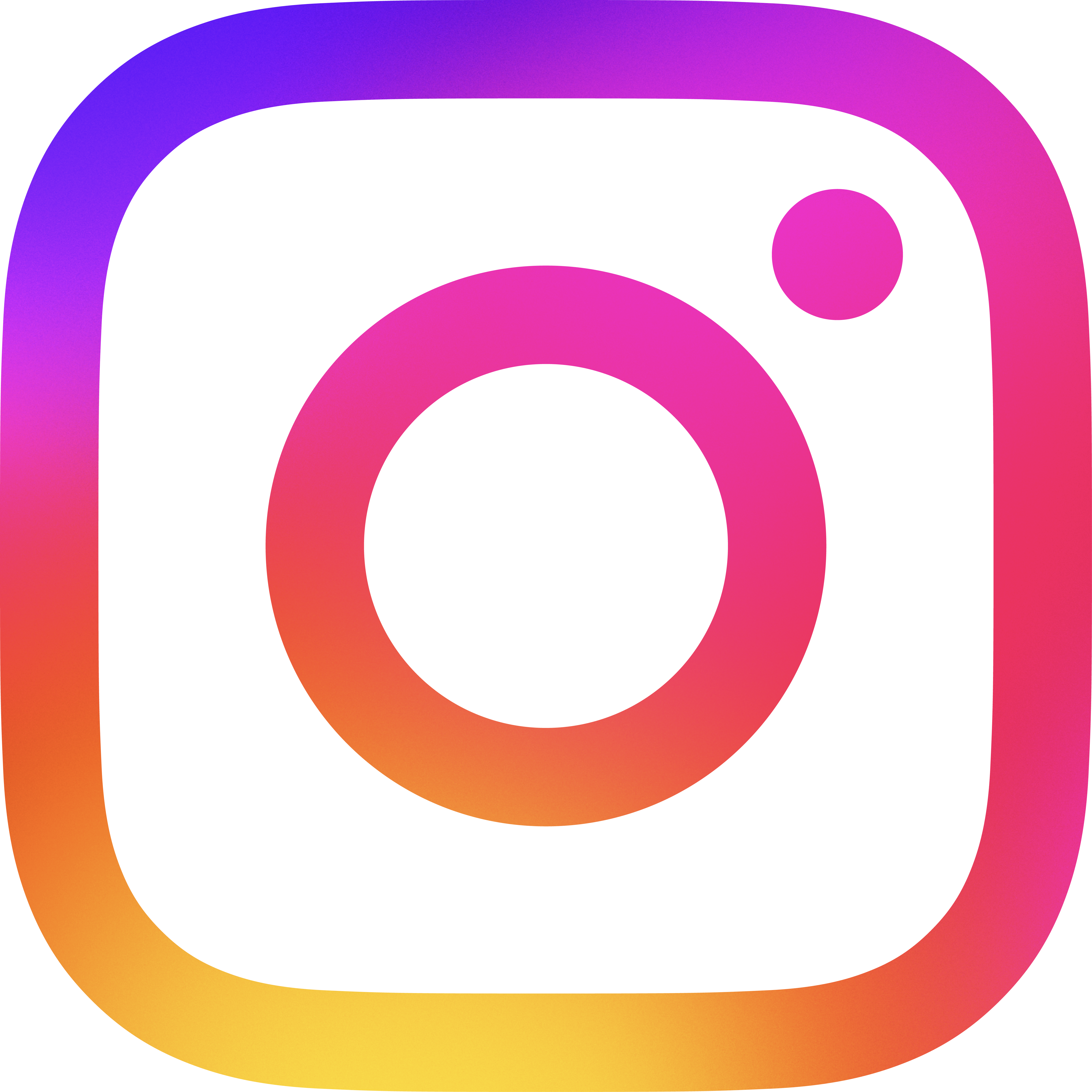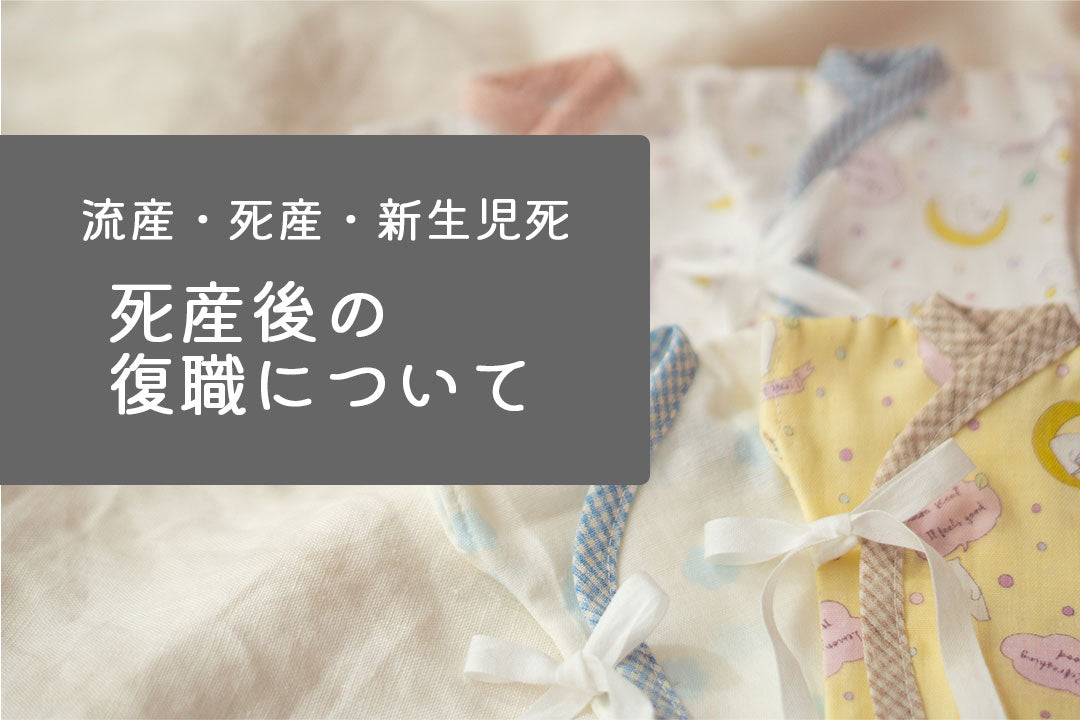
死産後の復職について

死産後の復職について
★死産後の産休取得状況
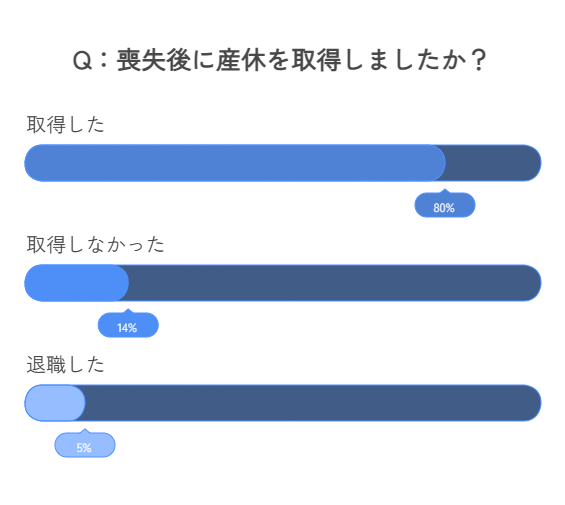

★産休後の復職状況
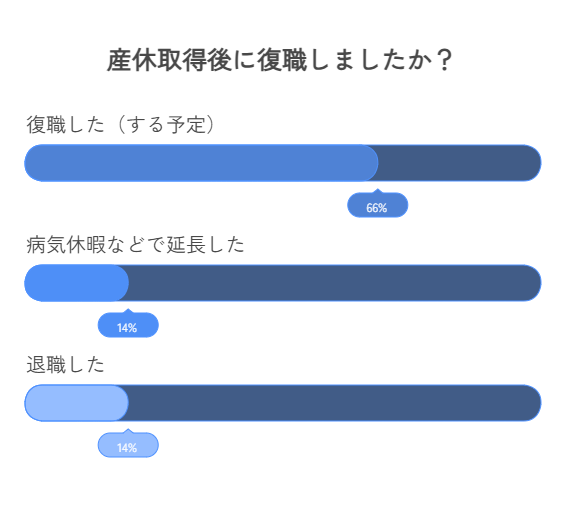
*働き方の変化について
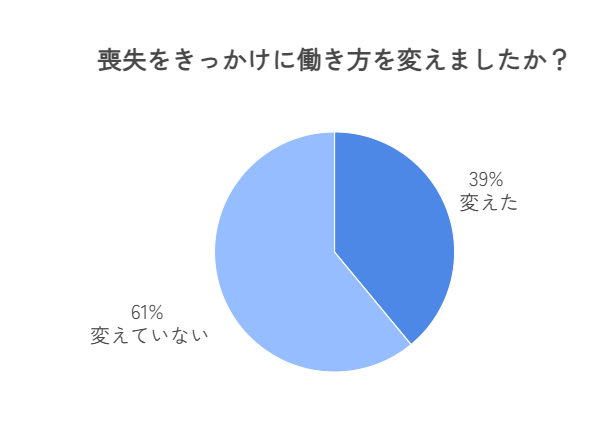

★会社への報告の仕方 - 実際の経験談
*上司への報告の仕方
*同僚への伝え方

★職場復帰時の注意点と対策
*周囲からの質問への対応
*配慮と孤立感のバランス
*会社制度の活用

★復帰後の働き方の工夫

★まとめ - あなたらしい社会との関り方を
Title
Title